一眼レフでの本格的な撮影が増え、撮影機材も多くなってきたら、カメラリグは必須アイテム。そろそろ購入しようかなと考えている方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回はカメラリグが初めての方のために、その選び方とおすすめ5選を紹介します。
まずは一覧表です。

①NEEWER
アルミニウム合金カメラ
ショルダーリグ

②SmallRig
汎用カメラケージ

③NICEYRIG
ショルダーマウント

④Zeadio
折りたたみ式ビデオリグ

⑤SmallRig
BMPCC 6K Pro用
ケージキット
それぞれの製品については、記事の後半でお伝えします。
カメラリグとは?初心者向けガイド
動画撮影をするとき、「手ブレがひどい…」「もっと安定した映像が撮りたい…」と思ったことはありませんか? そこで登場するのがカメラリグ。
カメラリグとは、撮影に使用する補助機材をカメラに取り付ける機材です。最近は、動画撮影する人の必須機材になっています。
でも、「そもそもカメラリグってどんなメリットがあるの?」と疑問に思う人も多いはず。
そこでこの章では、カメラリグの役割・必要性・取り付けられる機材・自作の可否について、初心者にもわかりやすく解説していきます!
(1)カメラリグの役割と必要性(動画撮影の安定性向上)
(2)カメラリグはどんな機材を取り付けられる?
(3)カメラリグの自作はお勧めしない
(1)カメラリグの役割と必要性(動画撮影の安定性向上)

動画撮影で一番困るのが手ブレ。カメラを手持ちで撮影すると、どんなに気をつけてもブレや揺れが発生します。特に長時間撮影すると、腕が疲れてきてブレがさらに悪化…。
ここでカメラリグの登場です。
なぜなら、カメラリグを使うと
- カメラを安定させる → 手ブレを軽減し、プロっぽい映像が撮れる
- 長時間の撮影が楽になる → ショルダーリグやジンバルで負担軽減
- 周辺機材を装着できる → マイク・ライト・外部モニターなど追加可能
ができるから、です。とくに、シネマティックな映像を撮りたい人にとって、カメラリグはマストアイテム。映画のような滑らかな映像を撮影するには、リグが大活躍します。
たとえば、手持ち撮影で走りながらのシーンを撮ると、画面がガタガタに。でも、カメラリグ(ジンバルやショルダーリグ)を使えば、スムーズな映像に!
もし、動画撮影を本格的にするなら、カメラリグは間違いなく必要です。
(2)カメラリグはどんな機材を取り付けられる?
さらに、カメラリグのもう一つの大きな役割は、「周辺機材を取り付けられること」です。
本格的な撮影をするなら、カメラ単体では正直足りません。たとえば、
- マイク → クリアな音声を録るために必須
- 外部モニター → 小さなカメラの画面では確認しにくいので便利
- ライト → 室内や夜間撮影で明るさを確保
- バッテリー&SSD → 長時間撮影用の電源やデータ保存
これらを一つのリグにまとめて装着できるのがカメラリグの強み。とくに、プロの現場では、リグなしでは撮影にならないレベルです。
また、最近はVlogやYouTube撮影向けに、小型のリグも増えてきています。たとえば、SmallRigのカメラケージなら、軽量でありながらマイクやモニターを装着できるので、クリエイターにも人気。
もし「とりあえずカメラだけでいいや」と思っているなら、それはもったいない!リグを導入することで、撮影の幅がぐんと広がりますよ。
(3)カメラリグの自作はお勧めしない

カメラリグを買うと、「意外と高いな…」「これなら自作できるんじゃ?」と思う人もいるかもしれません。でも、正直、自作はおすすめしません。
もちろん、PVCパイプ(塩化ビニールパイプ)や木材を使って、リグを作ることは可能。
ただし材料をカットして加工するためには、ノコギリや電動ドライバーなどの工具が必要です。
ものにもよるけど、数千円から購入できるリグも普通に売っているので、よほどオリジナルにこだわりたいという理由以外は、はっきり言って、購入した方が早いし、間違いないです。
カメラリグの種類と特徴
カメラリグと一口に言っても、実は色んな種類があります。
結局「どれを選べばいいの?」と迷う人も多いですが、結論から言うと、撮影スタイルに合ったリグを選ぶのが最重要ポイント。
- 長時間の手持ち撮影ならショルダーリグ
- 歩きながらの撮影ならステディカムやジンバル
- 手ぶれ補正を超強化するジンバル
- 滑らかなカメラワークを呼ぶスライダー
- 安定感と機動性の三脚リグ
それぞれの特徴をサクッと解説していきます!
❶長時間の手持ち撮影ならショルダーリグ
その名の通り、肩にのせて撮影するタイプのリグ。映画やドキュメンタリーの撮影現場ではよく使われています。
基本的に、両手でしっかりホールドできるので、手持ち撮影よりも安定感アップ! さらに、長時間の撮影でも腕が疲れにくいのがポイントです。
| 特徴 | |
|---|---|
| メリット | 手ブレを抑えながら、自然なカメラワークが可能 長時間の撮影でも疲れにくい 周辺機材(モニター・マイクなど)を装着しやすい |
| デメリット | ある程度の重量があるので、慣れが必要 コンパクトなVlog撮影には向かない |
| おすすめの人 | 映画風の撮影をしたい人 手持ちのブレを減らしたい人 |
❷歩きながらの撮影ならステディカム
つぎに、動画撮影でよくある「歩きながら撮ると映像がガタガタになる…」という悩み。普通にカメラを持って歩くだけでも、小刻みなブレが発生します。
そこで活躍するのがステディカムです。これは、カメラの重心をうまく分散させて、手ブレを物理的に抑えるシステム。とくに映画やCMの撮影では、今でも頻繁に使われています。
例えば、映画『ロッキー』の有名な階段ダッシュのシーン。あのスムーズなカメラワークは、まさにステディカムによるものです。
また、ステディカムを使うメリットは3つあります。
- 自然なカメラワークが可能
手ブレを抑えながら、歩きや走りの動きをそのまま映像に活かせる。まるで視点がカメラに乗り移ったような映像が撮れる。 - バッテリー不要で安定した撮影ができる
電動制御ではなく、物理的なバランスでブレを補正するため、バッテリー切れの心配がない。 - 本格的な映画撮影にも対応
ジンバルよりも重い機材を載せられるため、プロの現場では今でも使われる。
ただし、デメリットもある。
- 初心者が扱うにはコツがいる。
- バランス調整が必要で、慣れるまで時間がかかる。
- 機材が大きく、持ち運びには不向き。
結論として、ステディカムは「ガッツリ映画っぽい映像を撮りたい!」という人向けの本格派リグ。ただし、手軽にスムーズな映像を撮りたいなら、次に紹介するジンバルのほうがオススメです。
❸手ぶれ補正を超強化するジンバル
ステディカムと同じく、ジンバルも「手ブレを抑えてスムーズな映像を撮る」ための機材。ただ、大きな違いは電動モーターで自動補正すること。
簡単に言うと、手ブレ補正が超強化されたカメラリグ。例えば、スマホで撮影する際に「ジンバルを使うだけでプロみたいな映像になる!」という話を聞いたことがある人も多いのでは?
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 初心者でも簡単 | ステディカムと違い、バランス調整の技術が不要。ジンバルが自動でブレを補正してくれるので、誰でもプロっぽい映像が撮れる。 |
| コンパクトで持ち運びが便利 | Vlogや旅行動画を撮る人に最適。スマホ用ジンバルもあり、気軽に使える。 |
| モード切替で多彩な撮影可能 | 被写体を追いかける「フォローモード」や、360度回転する「ロールモード」などの映像表現ができる。 |
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| バッテリーが必要 | 長時間撮影するなら、予備バッテリーは必須。 |
| 重いカメラには不向き | 耐荷重を超えると、モーターが動かなくなることも。 |
結論として、ジンバルは「手軽に安定した映像を撮りたい」人向け。VlogやYouTube動画、ウェディング撮影などにも最適なリグです
❹滑らかなカメラワークを呼ぶスライダー
また、カメラをスムーズに動かしたいなら、スライダーは必須アイテム。
スライダーとは、レールの上をカメラがスライド移動するリグ。三脚の固定撮影と違い、前後・左右の微妙な動きを加えることで、映像に奥行きを生み出します。
例えば、映画のワンシーンで、被写体にゆっくり寄っていくカメラワークを見たことがありませんか?あれはほぼスライダーを使った映像です。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 映像がシネマティックになる | ゆっくり寄る、引く、横移動するだけで、映画のような雰囲気が出せる。 |
| ブレを気にせず撮影できる | 手持ちでカメラを動かすとブレるが、スライダーなら一切ブレずに滑らか。 |
| 商品撮影やインタビュー向き | 料理や商品紹介動画では、スライダーの動きを加えるだけでプロっぽくなる。 |
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 設置スペースが必要 | 短いスライダーなら省スペースで使えるが、長いスライダーは広い場所が必要。 |
| 長距離の移動には向かない | 別途、ドリーが必要 |
結論として、スライダーは「映像にワンランク上の表現を加えたい人」におすすめのリグ。
特に商品撮影や映画風の映像には欠かせません。
❺安定感と機動性の三脚リグ
三脚はただの固定ツールではなく、撮影の安定感と機動性を両立するための重要なリグ。
例えば、ライブ配信やインタビュー撮影では、「カメラを固定して、かつ周辺機材もセットアップしたい」ことが多い。そこで役立つのが三脚リグです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 圧倒的な安定感でブレゼロ | どんな状況でもカメラを完全に固定できるので、手ブレが一切ない。 |
| マイク・モニター・ライト 必要な機材をフル装備 | マイク・モニター・ライトなど、必要な機材をフル装備できる。撮影環境を完璧に整えられるため、プロの現場でも必須。 |
| 長時間の撮影に向いている | ライブ配信、インタビュー、ドキュメンタリー撮影などで活躍。 |
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 動きのある撮影には向かない | カメラが固定されるため、動きのあるダイナミックな映像には不向き。 |
結論として、三脚リグは「ブレのない安定した映像を撮りたい人」向け。
特に、長時間の撮影や配信には欠かせないアイテムです。
主なカメラリグのメーカーは?
「カメラリグを買おう!」と思ったときに、まずぶち当たるのがどのメーカーを選ぶべきか問題。
そこでこの章では、カメラリグを販売している、主なメーカーを紹介します。
①TILTA(ティルタ) → プロ仕様&ハイエンド志向
② SmallRig(スモールリグ) → コスパ最強!初心者~上級者まで幅広く対応
③ CAMVATE(カムベート) → カスタマイズ性が高く、特殊な撮影にも強い
④ Neewer(ニューアー) → とにかく安い!コスパ重視の人向け
①TILTA

TILTAはカメラリグの老舗メーカーで、少し値段が高いですが品質、使いやすさに定評があります。
「プロ仕様の本格リグを使いたい!」という人は、TILTA(ティルタ)一択。
剛性が高く、耐久性も抜群。特に、ブラックマジックやREDなどのシネマカメラ向けのリグが豊富なのが特徴です。
例えば、「TILTA Advanced Camera Rig」は、プロの現場でも使われるハイエンドなセットアップが可能。また、拡張性が高く、周辺機材をガッチリ装着できます。まさに“映像制作ガチ勢”向けのブランドです。
②SmallRig

多くの国内メーカーカメラに対応していて、リグの種類が多いことが特徴。とくに、SONYの一眼レフaシリーズなどの専用カメラケージなどあって、多くの人が使用しています。
そのため「コスパ最強のカメラリグが欲しい!」なら、SmallRig(スモールリグ)がベスト。
さらに、SmallRigは、プロも使うレベルの品質を維持しながら、価格がリーズナブル。しかも、カメラケージ・ハンドル・マウントパーツなどのラインナップが豊富です。初心者でも簡単にカスタマイズできるのが魅力です。
③CAMVATE

さらに「カメラリグを自分仕様にガッツリ改造したい!」という人向けなのが、CAMVATE(カムベート)。
こちらは、海外メーカーです。が、ほとんどのカメラに対応したリグを揃えています。
CAMVATEは、カスタマイズ性の高さが特徴です。そのため、自由にパーツを組み合わせて、オリジナルのカメラリグを構築できます。また、ハンドルやマウントパーツが豊富で、「市販のカメラリグじゃ満足できない!」というこだわり派のクリエイターに人気です。
例えば、「CAMVATE DSLR Shoulder Rig」は、ショルダーリグとしての基本機能を備えながら、追加パーツで細かい調整が可能。
とくに映画撮影や特殊なカメラワークを求める人にはピッタリのブランドです。
④Neewer

最後は、Neewerです。こちらのリグは他のメーカーに比べて比較的安価なものが多いです。そのため、アマゾンにも多く出品されており、購入しやすいのがポイント。
「とにかく安くカメラリグを揃えたい!」なら、Neewer(ニューアー)が最強。
また、Neewerは、エントリーモデルのカメラリグや撮影機材を格安で提供するメーカー。
例えば、「Neewer アルミニウム合金カメラショルダーリグ」は、ショルダーリグとしての基本機能を持ちつつ、価格は他メーカーの半額以下。とくに、初めてのカメラリグとして試すには最適なブランドです。
カメラリグの選び方のポイント
大きく4つのポイントに分けて、カメラリグの選び方を説明しています。
<1>用途別に選ぶ(Vlog / 映画 / イベント撮影 など)
<2>予算別に選ぶ
<3>ショルダーリグを選ぶ
<4>マウントの方法で選ぶ
<5>クイックリリースの種類で選ぶ
<6>より軽量な素材を選ぶ
カメラリグの選び方<1>用途別に選ぶ(Vlog / 映画 / イベント撮影 など)
カメラリグは、撮影の目的によって適したものが変わります。「どれを買えばいいか分からない…」という人は、まず自分の撮影スタイルに合ったリグを選ぶのがベスト。
1.Vlog・YouTube撮影向け
VlogやYouTube撮影では、カメラを頻繁に持ち歩くことが多いので、できるだけ軽量でコンパクトなリグが理想です。例えば、SmallRigのカメラケージなら、最低限の装備を追加しつつ、持ち運びの負担も少ないので、旅Vlogや日常系YouTubeにぴったり。
逆に、大きくて重いショルダーリグやジンバルは、Vlog撮影には向きません。スムーズな映像を撮りたくてジンバルを選ぶ人もいます。が、長時間の手持ち撮影には腕が疲れやすいです。なので、気軽に撮りたいならカメラケージ+小型ハンドグリップの組み合わせがおすすめです。
2.映画・シネマティック撮影向け
映画のような本格的な映像を撮りたいなら、ショルダーリグやジンバルが活躍します。ショルダーリグを使えば、手持ちのブレを抑えながら、ドキュメンタリー風のリアルな映像を撮ることができます。一方、ジンバルを使えば、スムーズでダイナミックなカメラワークが可能になります。
例えば、TILTAのショルダーリグは、プロ仕様の頑丈な設計で、長時間の撮影でも安定した映像が撮れるため、映像制作ガチ勢に人気があります。ただし、リグ自体の重量があるので、長時間の手持ち撮影をする場合は、バランス調整をしっかり行う必要があります。
3.イベント撮影・ライブ配信向け
イベントやライブ配信では、長時間の撮影でも疲れにくく、機材をしっかり固定できるリグが必要になります。特に、三脚リグやショルダーリグが活躍する場面が多く、手ブレのない安定した映像を撮るには必須のアイテムです。
例えば、Neewerのショルダーリグは、比較的軽量でコスパが良く、初心者でも使いやすいのが特徴です。また、ライブ配信なら三脚リグを活用し、カメラの位置を固定して長時間撮影できる環境を作るのがベスト。
カメラリグの選び方<2>予算別に選ぶ
カメラリグは、価格によってクオリティや機能が大きく変わります。
「とりあえず試してみたい」「ガッツリ本格的に撮りたい」など、自分の予算と目的に合わせて選ぶのが大事です。
| 対象者 | 内容 |
|---|---|
| 1万円以下 (初心者・とりあえずの人) | 「まずはカメラリグを試してみたい!」という人には、NeewerやUlanziなどのエントリーモデルが向いています。安価ですが、基本的なリグの機能は備わっています。そのため、Vlogや簡単な撮影には十分対応可能。ただし、耐久性はそこまで高くないため、長期間ガシガシ使うなら、もう少し上のグレードを検討するのもアリ。 |
| 1万円~3万円 (中級者向け・バランス重視) | この価格帯になると、SmallRigやCAMVATEのリグが選択肢に入ってきます。とくに、SmallRigのカメラケージやショルダーリグはコスパが良く、多くのクリエイターが愛用しています。また、軽量でカスタマイズ性が高いのが魅力で、Vlog撮影から映画撮影まで幅広く対応できます。 |
| 3万円以上 (プロ向け・本格的な撮影用) | 本格的な映像制作をするなら、TILTAやDJIのジンバルが視野に入ります。TILTAのショルダーリグはプロ仕様の頑丈な設計で、拡張性が高く、さまざまな機材を取り付けられるのが特徴。一方、DJIのジンバルは、スムーズなカメラワークを実現し、映画のようなダイナミックな映像が撮れます。 |
カメラリグの選び方<3>ショルダーリグを選ぶ
ショルダーリグとはその名の通り肩で支えるリグのことを指します。ショルダーパット、グリップが付いていて、ベースプレートに繋げて使用する形が多いです。
支点が増えることによって、疲労を減らす効果とブレを少なくする効果があります。

自分で必要な部分を揃えてショルダーリグを組み上げることも可能です。が、初心者の場合ショルダーリグのセットを購入する方法をおすすめします。
セットを使用しているうちにフォローフォーカスやマッドボックスなど、必要な部分が分かってくるようになります。
またショルダーリグは肩にあたる部分にクッションがあります。その素材によって長時間担いでいても疲労がおきないかなど、確かめることも必要です。場合によっては交換しましょう。
カメラリグの選び方<4>マウントの方法で選ぶ

モニターやバッテリー、ハンドルなどを付ける際の専用マウントはリグによって固定するネジの形状、サイズが異なります。
自分の持っている機材の規格とリグの規格が同じかを確認することが大事です。
カメラリグの選び方<5>クイックリリースの種類で選ぶ

クイックリリースの種類はそう多くありません。
が、例えばマンフロットのものを使いたいのであれば、マンフロットの規格に対応するものを選ぶ必要があります。
自分が使用したいクイックリリースも把握してリグを選びましょう。
カメラリグの選び方<6>より軽量な素材を選ぶ

カメラとその他の撮影機材を合わせると相当な重量になります。
その上にリグが重い素材であれば、持つのが大変です。
三脚に固定するのであれば問題ないかもしれません。が、手持ちでの撮影も考えている方は、カーボンなど軽量な素材のリグを選ぶのもオススメです。
おすすめのカメラリグ5選
ここからは、おすすめのカメラリグを紹介していきます。
本格的なものから低価格で購入できるライトなものまで、紹介しているので是非参考にしてください。
おすすめのカメラリグ①|NEEWER ショルダーマウントビデオリグ SR007

このリグは、最大5kgまでのカメラ機材をサポート。また、Arcaクイックリリースシステムを採用しています。
そのため、カメラの着脱が迅速かつ容易になりました。
さらに、撮影現場での機動性が向上します。
くわえて、SmallRigのカメラケージとも互換性があり、既存の機材との組み合わせもスムーズです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 安定性の向上 | ショルダーマウントデザインにより、手持ち撮影時のブレを効果的に抑制。滑らかな映像を実現します。 |
| 柔軟なカスタマイズ | 15mmロッドシステムを採用。フォローフォーカスやマットボックスなどのアクセサリーを追加した撮影のセットアップが可能です。 |
| 快適な操作性 | デュアルハンドル設計により、長時間の撮影でも疲労を軽減。安定したカメラ操作が行えます。 |
おすすめのユーザー
ショルダーリグは、長時間の手持ち撮影に適しています。安定した映像を求める方や、機材のカスタマイズ性を重視するユーザーにとって、信頼できるパートナーとなるでしょう。
おすすめのカメラリグ②|SmallRig 汎用カメラケージ

汎用カメラケージなので、ほとんどの一眼レフで使用することができます。
1/4,3/8穴が沢山あいているので、拡張性が高くカスタマイズがしやすいのがポイント。
自分でシステムを組んでいきたい方におすすめ。
このカメラケージは、Vlog・YouTube撮影向けのリグとして人気。
小型ながら、マイク・LEDライト・モニターなどを自由に取り付けられる拡張性の高さが魅力です。
おすすめのカメラリグ③|NICEYRIG ショルダーマウント

人間工学に基づくデザインで、肩への負担が軽減。
ショルダーパッドは素材が柔らく、肩にかかる荷重を分散します。
ハンドルの手持ち部は本革レザーで、柔らかくて心地良く、長時間撮影の手の痛みを軽減します。
本レザーが滑り防止にも効果を発揮。 高品質なアルミニウムとメッシュ材料を使っているので軽量で丈夫です。
このリグは、パーツの組み換えが自由自在で、撮影スタイルに応じてリグの形を変えられるのが特徴。たとえば、ショルダーリグとしても、手持ちリグとしても使えるため、1台で複数の用途に対応できる優れものです。
「自分好みにカスタムしたい!」という人にピッタリです。
おすすめのカメラリグ④|Zeadio折りたたみ式ビデオリグ

Zeadio折りたたみ式ビデオリグは、幅広い互換性をもった折りたたみ式のカメラリグ。
ダブル1/4ネジで、一眼レフ、スマホ、GoProなどさまざまなデバイスに対応します。
また、安定したショットを撮影するための多機能スタビライザーで、手ブレを効果的に軽減できます。
さらに、バックルを押すことで、両手モードと片手モードに素早く切り替え。そのうえ、折りたたみ式構造設計でスペースを節約することができます。
くわえて、水平を取る水準器も装備。三脚に接続して、安定した撮影も可能です。
おすすめのカメラリグ⑤|SmallRig BMPCC 6K Pro用ケージキット

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro(BMPCC 6K Pro)を使っているなら、SmallRig BMPCC 6K Pro用ケージキットはマストアイテム。
モニターにカバーがついて、直射日光でも液晶画面を見やすい設計です。
NATOサイドハンドル2187は、ケージの左右どちらにでも使用可能。ハンドルの接続部を外して、反対側に装着だけでOK。
手にしっくりなじむ木製仕様で、ホールド感が抜群です。
手持ち撮影の安定性や、周辺機材の拡張性を考えると、リグの導入はほぼ必須。このケージキットを使えば、マイク・外部モニター・SSD・バッテリーグリップなどをスムーズに装着できるので、プロ仕様の撮影環境を構築できます。
カメラリグで本格的な撮影を!

今回の記事では、カメラリグについて詳しく説明しました。撮影機材が増えると、それを設置するのに時間がかかったり、無理やりつけると不恰好な配置になりがちです。
そんな時はカメラリグを使えば、スッキリとまとまり使いやすさもアップするのでオススメです。是非カメラリグ選びの参考にしてください。
>> Adobe Premiere 映画風に動画を編集する方法|上下にクロップを入れる理由も
今回も最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!















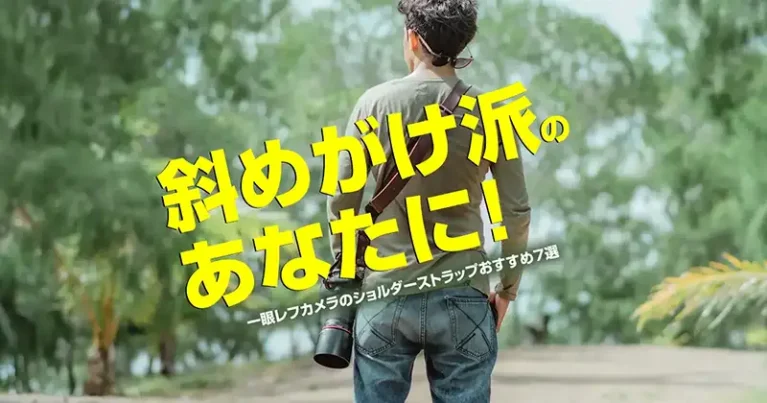




コメント