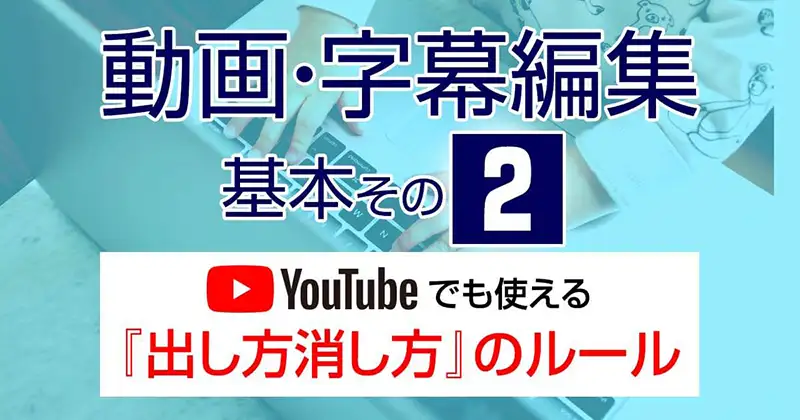
動画編集で動画に字幕テロップを入れると、それだけで視聴者が理解しやすい動画になります。
でも、動画の字幕テロップも入れればいいって訳じゃありません!テロップには入れ方の基本があるのです。
そこで、今回は
●字幕テロップのイン点とアウト点は?
●字幕テロップを表示しておく時間
●台詞が短い時のテロップの表示の仕方
などをお伝えする記事です。
どうぞ最後まで、ご高覧ください。
目次
テロップを出すタイミングと『出し方』『消し方』のルールは?
まず、最初に結論をいうと、テロップを出すタイミングに絶対のルールはありません。
が、かならず押さえておくべき基本はあります。
基本から外れたものは、見ていてどこか違和感のある動画になるので、次の3点に注意して作業をしましょう。
①イン点とアウト点(テロップを出す、消すのタイミング)
②テロップを表示する時間と3つのポイント
③短いセリフのテロップ消し方
です。一つずつお話しさせて下さい。
①イン点とアウト点(テロップを出す、消すのタイミング)
基本のイン点は、セリフのしゃべり出しです。
このとき、ぴったりに出すか?もしくは編集単位で5フレーム手前から、テロップを出すようにしましょう。
しゃべり出してからのテロップは、非常に気持ち悪い映像になるのでNGです。
逆にアウト点は、しゃべり終わりから1秒後に設定します。
②テロップを表示する時間と3つのポイント
基本的に、テロップを表示したい時間は「3〜4秒」です。
ただし人がしゃべる言葉は、長いものから短いものまであります。
それぞれの対応方法を表にまとめました。
| 台詞の時間 | 表示方法 |
|---|---|
| ❶テロップ表示時間とセリフ時間が3秒以上の場合 | セリフのしゃべり出しから3〜4秒表示 |
| ❷極端にセリフが短い(1秒以内)場合 | セリフが終わってからもテロップを最低3秒間は表示 |
| ❸短いセリフが連続する場合 | 最初にテロップを下に出して、次は、その上。その次は左側、など、場所を変えて表示させる |
もう少し詳しくお伝えします。
❶テロップ表示時間とセリフ時間が3秒以上ある場合
この場合は、セリフのしゃべり出しから3〜4秒表示しましょう。
❷極端に短い時間(1秒以内)の場合
「オッケーです」とか「いいね」とか1秒もしゃべらない場合でも、テロップを出したいときがありますよね。
その場合、しゃべる時間に合わせてしまうと、どうなるでしょうか?
テロップが出たり、消えたりして、まるで点滅しているみたいだと思いませんか?あんまりテロップがせわしなかったら、そっちが気になって、動画どころじゃありません。
じゃあ、そんなときには、どうするのか?というと、セリフが終わってからもテロップを最低3秒間は表示したままにするようにします。
❸短いセリフが連続する場合
さらに短いセリフが連続で続いた場合はどうなのか?という問題もあります。たとえば
「吉田です」
「どこにお住まいですか?」
「千葉県です」
みたいな場合です。
テロップの表示時間は、基本3〜4秒。
なので、そんな場合にも、3〜4秒はテロップを見せる工夫が必要になります。
この場合は、最初にテロップを下に出して、次は、その上。その次は左側、など、場所を変えて表示させるといいでしょう。
③短いセリフのテロップ消し方
テロップを表示させたら、消し方もポイントになります。
最初に出したテロップは、すぐに消さずに出したままにします。
理由は、テロップを消すという行為で、動画に、ポイントというか『傷がついてしまう』から…です。
すぐにテロップを消すと画面が傷つく
そして、場面代わりや、しゃべり終わりのタイミングに合わせて、全部まとめてテロップを消すようにすると、動画がスッキリと見られるようになります。
字幕テロップはカットか?フェードか?

ここでは、テロップのタイミングではなく、出し方についてお伝えします。
テロップを『ピッタリ出すか?』『フェードインで出すか?』についてお話しします。
(1)テンポ感が欲しい時はピッタリ出す
(2)シリアスで重たいテーマならフェードイン&フェードアウト
これは演出上の問題として、2点に注意しましょう。
(1)テンポ感が欲しい時はピッタリ出す
コメディタッチであったり、バラエティのようなテイストの場合には、ピッタリ出して、消す。
というテロップの出し方がオススメです。その理由は、ピッタリと出した(消した)方が、動画にテンポ感が出るから。
動画のリズムが悪くなるし、見ていてまったりしますよね?
(2)シリアスで重たいテーマならフェードイン&フェードアウト
逆に、フェードイン、フェードアウトを使うのは、重たいテーマであったり、シリアスな状況です。
じっくりと読ませたり、あるいは動画に余韻を残したいときには、フェードイン&アウトのテロップが効果的です。
動画のテーマや使う目的に合わせて、上手に使い分けて行きましょう。
テロップの基本的な考え方2点

最後に、最低限考えておかないといけないテロップの基本を2点お伝えします。
<1>動画の演出は無限にある
<2>より見る人を意識して作らないといけない
このあたり、ちょっとこだわりたいので、その意味をご説明します。
<1>動画の演出は無限にある

動画での演出は、無限にあります。
文字の大きさや種類に加えて、背景の素材や、テロップを出すタイミング、出し方&消し方(フェードアウト、フェードインなど)さまざまな効果を細かく設定することが可能です。
その演出具合は、動画全体の『色』を左右します。
動画を見る機会の増えた昨今、同じように見る人の目も肥えていますから、テロップの入れ方一つで、どんな演出が施されているか?さえも判断されてしまうのです。
<2>より見る人を意識して作る

当たり前の話ですが、私たちは、動画を見る人を意識したテロップづくりを心がけています。
そうやって考えると、もはやテロップは『美術品』という位置付けで扱うべきものだと感じています。決して手を抜くことはできません。
テロップを軽視した動画は、見る人にとっては『違和感』さえ感じさせてしまうでしょう。
動画編集|字幕テロップ(その2)まとめ
まとめ.webp)
さて、テロップ論について、長々とお話ししてきましたが、基本となる考え方は一つだけ。
『メインの素材である映像と音をアシスト』です。
まとめると
①イン点とアウト点(テロップを出す、消すのタイミング)
②テロップを表示する時間と3つのポイント
③短いセリフのテロップ消し方
| 台詞の時間 | 表示方法 |
|---|---|
| ❶テロップ表示時間とセリフ時間が3秒以上の場合 | セリフのしゃべり出しから3〜4秒表示 |
| ❷極端にセリフが短い(1秒以内)場合 | セリフが終わってからもテロップを最低3秒間は表示 |
| ❸短いセリフが連続する場合 | 最初にテロップを下に出して、次は、その上。その次は左側、など、場所を変えて表示させる |
(1)テンポ感が欲しい時はピッタリ出す
(2)シリアスで重たいテーマならフェードイン&フェードアウト
<1>動画の演出は無限にある
<2>より見る人を意識して作らないといけない
でした。
最初から、完璧には行きません。でも、『最初に作ったものが、一番下手くそな作品』です。
作れば作るほど、上手になっていきますから、どんどん、作って行きましょう。
そしてわからないことがあれば、どしどしご質問ください。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
動画制作や映像・撮影機材・Adobe製品の専門メディア『VideoLab』
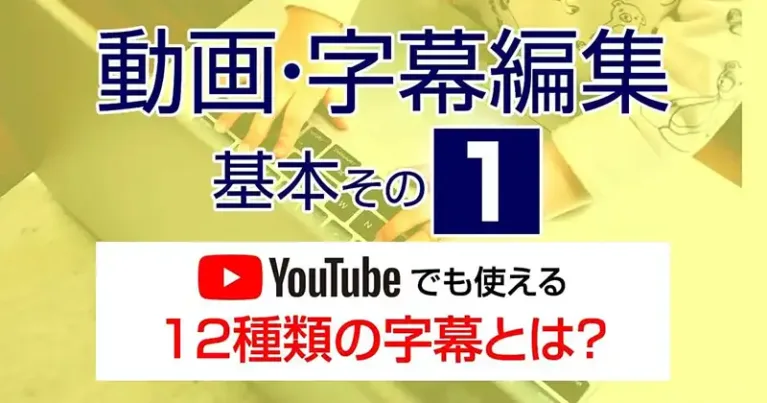
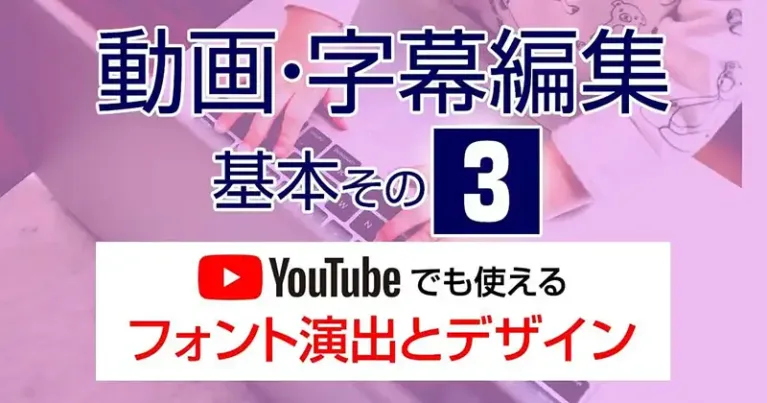
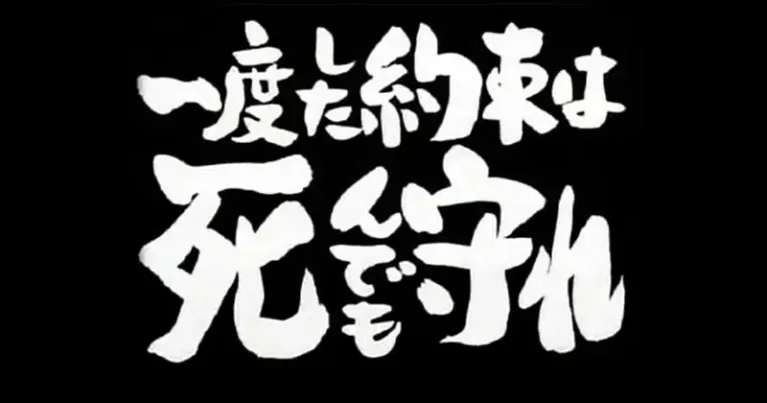


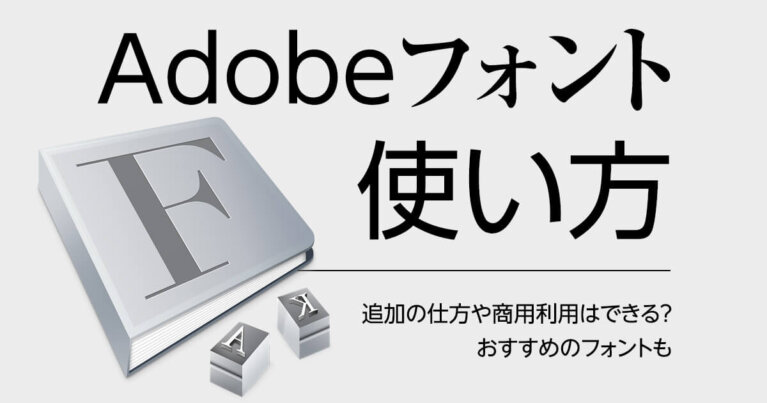



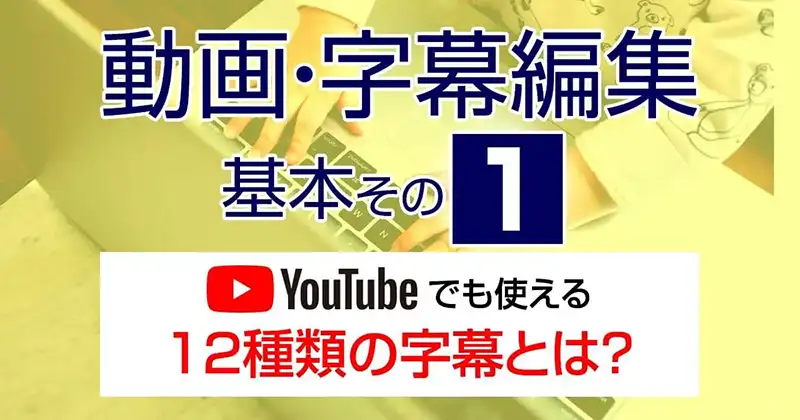








![Davinci Resolveで学ぶ映画風カラーグレーディングの基礎[フィルムルックに挑戦]](https://videolab.jp/wp-content/uploads/2022/11/Davinci-Resolveで学ぶ映画風カラーグレーディングの基礎フィルムルックに挑戦--600x600.webp)



